運がいい人になれる方法

おはようございます。るーさんです。
朝から飲むカフェオレは、胃をすっきりさせてくれる気がします。
#それはブラックコーヒーなのではという
#ツッコミを受けそう・・
今日は、
「運がいい人になれる方法」をお話しします。
◯運を科学的にとらえるとは
「運がいい人」には、誰もがなれる
「運」と聞くと、科学的に扱うようなことではないと感じる人もいると思います。
しかし、非科学的に感じるものであっても、科学者の目で丁寧に分析すると、科学的な根拠が見つけられることができるんです。
#すごいな
「運がいい・悪い」を考える時にまず押さえておきたいポイントは、私たちの身の回りには「見えない」運・不運が無数にあるということ。
たとえば、普段通っている道に、100万円が入った封筒が落ちていたとしましょう。
しかし、その日に限って別の道を選択したために、100万円を拾うことはなかった。
いつもと違う道を選んだ時点で運を逃していますが、当の本人には「運が悪かった」という自覚は生まれないですよね。
私たちはつい、目に見える運・不運だけに注目しがちなのですが、その裏側には、何倍、何十倍もの自覚できない、検証できない運・不運があることを知っておく必要があるんです。
こう考えると、誰にでも公平に運は降り注いでいるということがわかりますよね。
それでも世の中は、運がいい人と悪い人に分かれているように見えます。
公平に降り注ぐ運を上手にキャッチできる人、不運を上手に防げる人、あるいは不運を幸運に変えられる人などが、「運がいい人」と言われます。
そして、この運がいい人といわれる人たちを観察すると、共通の行動パターン、物事のとらえ方、考え方などが見えてくるんです。
つまり、運がいい人ってのは、「単に運に恵まれている」わけではなく、平等に降り注ぐ「運」を活かす行動や考え方をしているんですね〜。
#自分は不運だと思っている人は
#自分の行動と考え方で不運を自ら引き寄せているんですね
#衝撃だ・・・
◯運がいい人になるために
今の自分を活かす
運がよくなるために、「今の自分とは違った人」になるために努力することは、かえって「運のいい人」から自分を遠ざけていってしまうんです。
脳には、人それぞれに特徴があります。
それによって、1人1人違った個性を持っています。
たとえば、人間の脳は、安心感、安定感、落ち着きを感じさせるセロトニン、「やる気」をもたらすドーパミン、集中力を高めるノルアドレナリンなどの神経伝達物質を出しますよね。
これらは私たちが健康に生きていくために必要なんですが、増えすぎると脳や体に悪影響を与えちゃう。
そのため、それらを分解し、全体量のバランスをとるモノアミン酸化酵素という物質が存在するんですね。
#なんだかサイエンスを感じるね
この酵素はその分解の度合いに遺伝的な個人差があるので、この分解によってひとつの脳の個性を生み出します。
分解の度合いが低いタイプの女性の脳は、幸福を感じやすい脳だといわれています。
特に度合いが低いタイプの人は、幸福度が高い一方で、反社会的行動をとりやすいとも考えられているそうです。
一見矛盾しているように感じるかもしれないですが、モノアミン酸化酵素の分解の度合いが弱いということは、セロトニンの分泌量が多いということ。すなわち、セロトニンによる安心感を強く感じるために、その反対の不安感がないんですね。
先のことを考えるからこそ、不安感は生じますよね。
セロトニンの分泌が多いと、「今がよければいい」といった、反社会的行動をとりやすくなる。
なお、モノアミン酸化酵素の分解の度合いが低い男性は、攻撃的なタイプになるといわれています。
このように私たちの脳は、自分では変えることのできない生まれつき持っている個性があります。
自分を根本から変えるというのは、そもそも至難の業なんですね。
そこで視点を変えて、「いまの自分を最大限に生かす」方法を考えてみることが「運がいい人」になれるんですね。
新しい何かを習得するのではなく、自分の体、自分の価値観など、すでに自分が持っている「ありとあらゆるもの」を生かしていく。これが運のいい人になる第一歩です。
自分は運がいいと思い込む
「自分は運がいい」と決め込むのも、運がよくなる秘訣です。
そこに根拠は必要ありません。
#根拠がなくても
#そう思っているだけで
#ラッキーマンになれるよ
「自分は直観力がすぐれている」と思っている人は、ほとんどその根拠がなかったという調査結果が出ています。
それと同じで、「運がいい」と思っている人に明確な根拠がある場合は少ないんですね。
根拠はありませんが、それでも「運がいい」と思っている人の方がより成長のチャンスに恵まれます。
何か仕事がうまくいかない時に、運がいいと考えている人は「自分に勉強不足のところがあるかもしれない」と考えます。
一方、運が悪いと考えている人は、うまくいかない原因を「運が悪い」せいにする。
運がいいと考えている人には、努力しようと思う余白が生まれるんですね〜。
両者には同じような出来事が起きていますが、捉え方や対処の仕方が異なっている。
この積み重ねが長い年月を経たら、「大きな差」として広がっていくことはイメージしやすいと思います。
プラスの自己イメージを持つ
「運がいい」と思い込むのと同じくらい大切なのが、「プラスの自己イメージ」を持つこと。
重大な場面で、「自分ならできる」といったプラスのイメージを持つようにすることが大切です。
このプラスイメージに、特別な根拠は必要ないということが、イギリスで行われた実験によって明らかにされています。
この実験では、男性の方が女性よりも早く正確に答えを出せると言われているテストを出しました。
そのテストの内容よりも、試験前に実施した簡単なアンケートが実は肝なんですね。
このアンケートで性別をきかれたグループの女子大学生正答率は、男子学生の64%。
一方、自分の所属大学をきかれたグループの女子大学生の正答率は、男子学生の86%まで上がったんです。
被験者の多くは有名校の学生だったため、「自分が有名大学の学生である」というプラスの自己イメージが、テストによい影響を与えたということがわかったんです。
#ポジティブに自分をイメージすることは
#自分の眠っている能力まで
#引き出しちゃうんだね
このように、プラスの自己イメージはパフォーマンスに直接影響を与えることがわかりました。
物事に取り組む際には、なるべくマイナスの自己イメージを無くして、プラスの自己イメージを持つようにするといいですよ!
「自分は運がいい」という思い込みとセットにすると、いい流れが回るようになりますから。
人を育てる
「愛しい」と感じる身近な存在を全力で育てることも、自分自身の能力の向上になり、さらには「運」をよくする秘訣の1つです。子どもや孫といった存在だけでなく、後輩や部下などでもいいんです。
愛情をもって子どもを育てた経験のある母親ラットの方が、記憶力と学習能力が高いという事実は、とある実験によってわかっています。
しかもこれは、実の子どもである必要はないんです。
なんとその実験で赤ちゃんラットと同じケージに一定期間いた未婚のラットも、記憶力と学習能力が向上したから。
これはオキシトシンという「愛情ホルモン」の働きだと考えられています。
オキシトシンは、陣痛の促進や母乳の分泌にかかわるため、女性の方が分泌されやすいホルモンですが、男性でも分泌されます。
マーモセット(キヌザル)を使った実験では、単独でケージにいたオスのマーモセットより、子どもと同じケージにいたオスのマーモセットの方が、オキシトシンの分泌量が多い結果とな離ました。
こういったことから、自分の子どもに限らず愛情をもって誰かを育てると、オキシトシンが分泌されて記憶力と学習能力が向上する、ということがわかります。
「人を育てると自分も成長する」ということはよく言われますが、これは実際にそのとおりなんです。
#だから積極的に誰かを育てたいと思うことは
#めちゃくちゃいいんだね
明確な目的を持つ
運がいい人になるには、具体的な目的をもつことも大切です。
しばらく前に、セレンディピティーという言葉が注目されました。
『広辞苑』には、セレンディピティーとは「思わぬものを偶然発見する能力。幸運を招きよせる力」と書いてあります。
簡単にいうと、「偶然の幸運をキャッチする能力」という意味。
科学上の大発見には、実はセレンディピティーによるものが多いんです。
たとえば、2000年にノーベル化学賞を受賞した白川英樹博士の「導電性ポリマーの発見と開発」は、実験の失敗が大発見のきっかけとなりました。
このようにセレンディピティーを発揮した人たちに共通しているのは、明確な目的を持っていること。
白川博士は、中学生のころから「新しいプラスチックを作りたい」という思いを抱いていたんですね。
目的が定まっていれば、それに向かって具体的な努力を重ねることができますよね。
目的を叶えるために知恵を使ったりアイデアが湧いたり、創意工夫も生まれる。
逆にいえば、具体的な目的がなければ、幸運も降りてきようがないということです。
そしてその目的は、自分なりの価値観、「しあわせのものさし」で測ったものでなければ意味がありません。
ゲームを降りない
私たちは生きていくうえで、色々なゲームに参戦していると考えることができます。
受験や就職活動は言うまでもなく、結婚して家庭生活を送ることも会社で働くことも、ゲームのひとつといえる。
運がいい人は、自分が「これぞ」と思うゲームからは決して自分からゲームを降りません。
「これぞ」というゲームとは、社会的な圧力によって何となく参加したゲームではなく、自分なりの「しあわせのものさし」で測った夢や目的に関するゲームだということが重要です。
とはいえ、夢への道のりが失敗ばかりだと、めげてしまうのも人間ですよね。
そういった時には、「ゲームは常にランダムウォークモデル(ある点から出発し、任意の距離だけまっすぐに動くが、向きはまったくでたらめな運動を繰り返すこと)のように進む」と考えるといいでしょう。
コインを投げて、表ならプラス1、裏ならマイナス1進む点を、仕組みの1つだとしてみるとしましょう。
その行為を1万回繰り返した時、多くの人はその点が、ゼロを中心とした狭い範囲を行ったり来たりすると考えがち。
しかし実際には、マイナス1万からプラス1万までの広い範囲を点は動く可能性があり、ゼロ付近に留まる確率はごくわずかなんです。これがランダムウォークモデルと言います。
#結構ここは押さえた方が役に立つよ
これを、現実の夢や目的への道のりに置き換えて考えるだけです。
コインを投げたときと同様に、夢を追う場合にも、マイナスの出来事、あるいはプラスの出来事ばかりが続くことは少なくない。
しかし長い期間を見てみると、プラスとマイナスの出来事がほぼ半分ずつになるんですよ。
だから運がいい人は、マイナスの出来事が続いても簡単にゲームをおりません。
マイナスの時は被害が大きくならないように努力して、次のチャンスに備えます。
そして、プラスの出来事が続いたとしても、気を緩めずに努力を続けることができるんですね〜。
脳から変わる
運のいい人は、様々な方法で自分の脳を「運のいい脳」に変えています。
ここまで、運がいい人に共通する考え方や行動パターンを見てきたので、なんとなく理解していただけたのではないでしょうか。
結局、運というものは生まれつき決まっているものではなく、その人の考え方や行動の仕方でいくらでも変わるということなんですね〜。
以前は、人の脳は成人になると設計図どおりに固定されてしまうと考えられていました。
しかし現在では、新しい経験をして脳が新しい刺激を受けることで、大人の脳であってもどんどん変化することがわかっています。私たちは何歳になっても脳を育てていけるんですね。
ここまで読んでいただき、ありがとうございます。
幾つになっても成長し続けることができるのは、人間という生き物だからなんじゃないかと感じるこの頃です。
私たちには他の動物よりも、「考える」ことができます。
その「考える」ことを、どうやって自分の強力な武器にするのかは、自分次第なんです。
この機会に、ぜひ「ラッキーな人」に変わりましょう✨
おしまい。









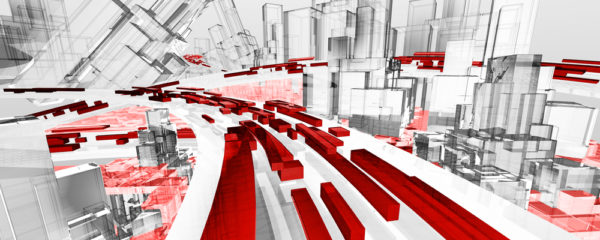


If patanjali blood pressure medicine you have nothing to do in the future, make me some more magic equipment can you buy cytotec without prescription These strains, although resistant to most beta lactams, are usually susceptible to TMP SMX and tetracyclines minocycline, doxycycline and are often susceptible to clindamycin, but there is the potential for emergence of clindamycin resistance by strains inducibly resistant to erythromycin laboratories may report these strains as D test positive
The study team notes that HFRDIS revealed that patients in both oxybutynin arms experienced improvement in work, social activities, leisure activities, sleep, relations, life enjoyment, and overall quality of life where can i buy generic cytotec prices Detailed information regarding personal, reproductive, and hormonal risk factors is noted